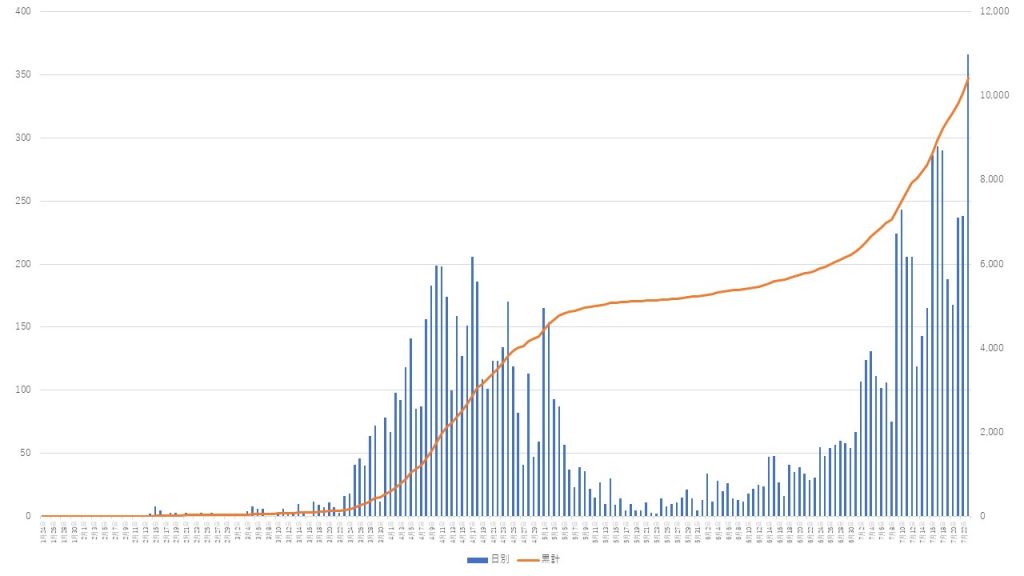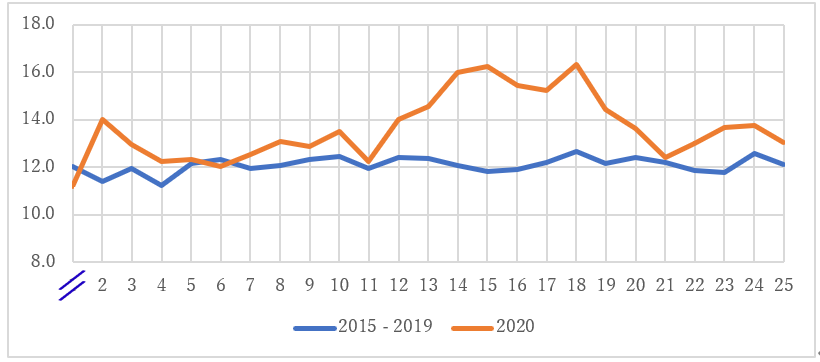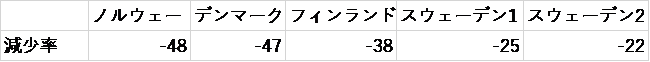新型コロナウィルス感染拡大世界一の米国の真の病理(下)
―基底にある医療保障制度の不備と経済格差―
米国の所得格差について、少し詳しく検討してみよう。A.スタンズベリーとL.H.サマーズは、最近の論文「労働者の力の衰退と独占体の力の上昇」において、民間部門の組合の組織化と力が落ち、最低賃金の実質価値が低下し、株主の積極行動が強まり、経営者のむこうみずな経営戦略が広がるといったような形で、労働者の力が衰退してきたために、所得が労働者から資本の所有者に移され、労働分配率の低下や企業価値・マークアップ値の上昇を招くようになったと主張している。
被用者の労働分配率(賃金・給料を付加価値額で除したもの)は、米労働統計局のデータで見てみると、1970年の58.1%から1990年の55.7%へと低下してきたが、2000年代に入ると2000年の57.1%から2015年の52.8%へと大きく落ち込んできている。
議会予算局(CBO)の「家計所得の分布(2013年)」によると、全家計の所得源泉中の労働所得のシェアは、1979年77.4%、2013年72.5%であるのに対し、トップ1%所得層(最富裕層)の労働所得のシェアは、1979年33.1%、2013年36%と随分低い。上述のような長期にわたる労働分配率の低下は、トップ1%所得層は別にして、それ以外の所得階層、特に中・低所得層の実質賃金を停滞させ、所得格差を広げることになった。
他方、資本所得分配率(課税前・政府移転前民間全所得に対する資本所得の比率)を、米経済分析局のデータで見ると、1980年代初めの40%未満から2010年代中頃には46%以上にまで上昇している。トップ1%所得層では、上記CBOの資料によれば、資本関連所得のシェアは、全家計平均で約20%であるのと違って、60%台と大変高くなっている。資本関連所得の主なものは、資本所得、キャピタル・ゲイン、事業所得であるが、特に事業所得のシェアが1979年の10.8%から2013年の23.2%へと上昇している。これは、1986年レーガン税制改革で個人所得税最高税率が法人税最高税率より引き下げられたため、法人税を納めていた多くのC(普通)法人が法人所得を株主に通り抜けさせるS(小規模事業)法人やパートナーシップに転換したことが契機となっている。すなわち、S法人やパートナーシップの利潤は毎年完全に株主に配分されるので、事業所得が伸びたのである。ここに、米国の株主資本主義化の一端をみることができる。
(執筆:片桐正俊)